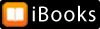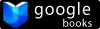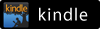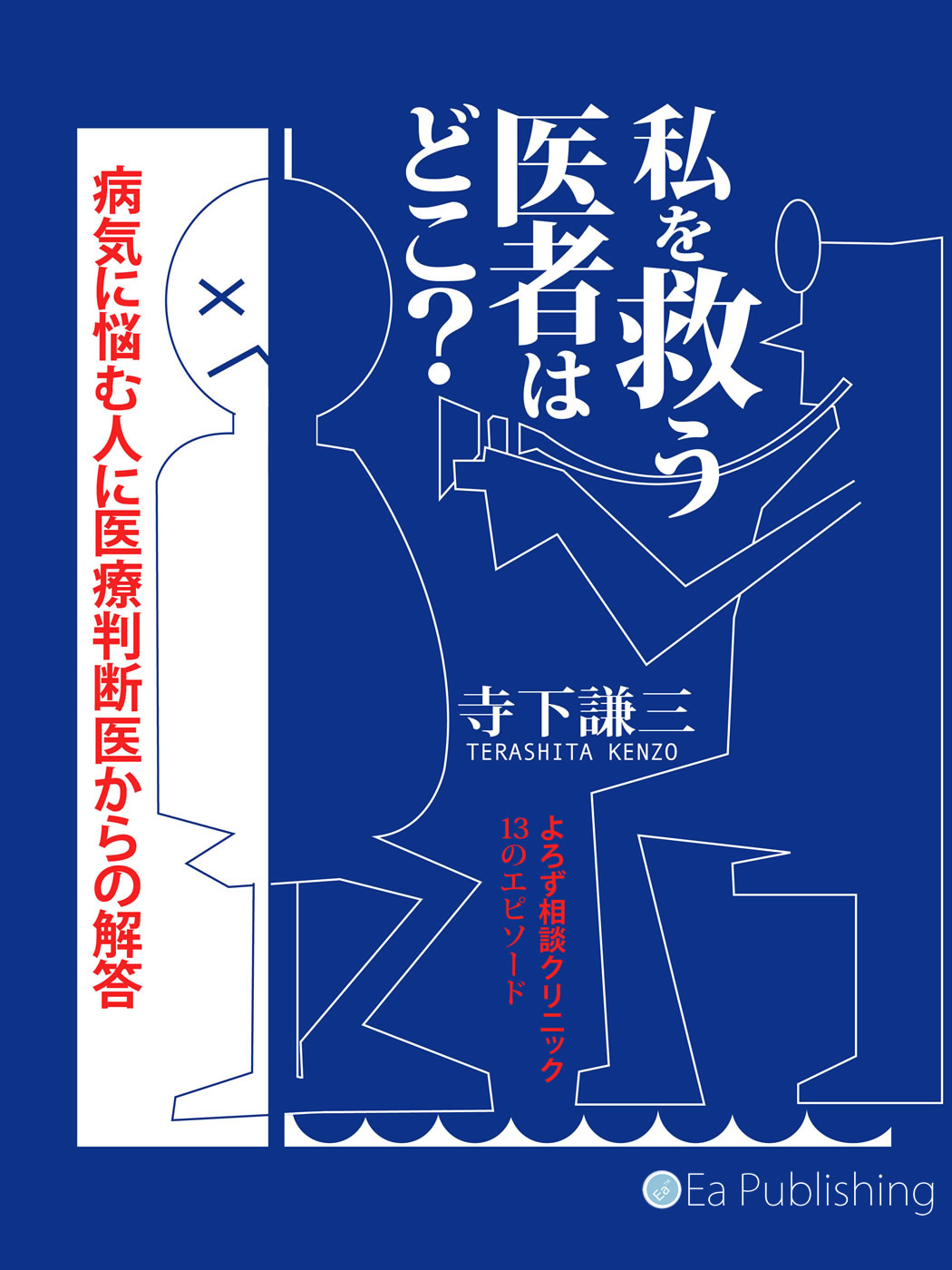-
今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)
・12月(師走/December)
・19日
・木(Thursday)
・二十四節気
┣「大雪」から12日
┗「冬至」まで3日
・先負
・十支:庚(かのえ)
・十二支:寅(とら)
月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)
 肝硬変と食道静脈瘤(肝硬変)【かんこうへんとしょくどうじょうみゃくりゅう(かんこうへん)】
肝硬変と食道静脈瘤(肝硬変)【かんこうへんとしょくどうじょうみゃくりゅう(かんこうへん)】- 肝硬変とは、その言葉のごとく肝臓が硬くなり、外観が萎縮(いしゅく)し表面は凹凸(おうとつ)不整になった状態をさします。これはウイルス肝炎やアルコール性肝炎、その他の慢性的な肝臓病が長期間続いた結果、肝細胞が死に、その再生過程で線維増生が起こった結果であり、いわゆる肝臓病の終末像です。また肝硬変になると脾臓が大きくなる脾腫(ひしゅ)を伴うことが多く、様々な症状を呈します。肝硬変の症状を理解するためには肝臓の働きを知る必要があるので、簡単に解説します。
《肝臓の働き》
[1]体に必要な様々な物質を合成する
肝臓は体に必要な様々な物質を合成する大切な機能があります。例えば血液凝固因子は肝臓でつくられるので、肝硬変では程度の差はありますが出血が止まりにくくなります。また血液中のアルブミンというタンパク質も同様に肝臓で合成されます。肝硬変では血清アルブミンが低下し、これが腹水発生の原因の1つとなります。コレステロールも肝臓でつくられるので、肝硬変では血清総コレステロールが低下します。
[2]門脈血(もんみゃくけつ)の流れ道
胃、小腸、大腸、膵臓(すいぞう)、脾臓を流れてきた血液が一緒になり肝臓へ流れ込む時、通る血管のことを門脈といいます。この門脈は肝臓内で次第に細くなり、やがて肝細胞と接し、様々な物質の交換を行い、肝静脈に流れていきます。健康な肝臓であればこの門脈の中の血液はスムーズに肝臓を通り、心臓にいきます。しかし肝硬変では肝の線維化のためこの流れに対する抵抗が増大し、その結果、門脈の中の血液の圧力が高くなります。この状態のことを門脈圧亢進(こうしん)症といいます。この血液は肝臓を通って心臓に戻るのが困難なので、他の経路を探します。その結果、探しだした経路が食道静脈瘤(りゅう)や腹壁静脈拡張、あるいは痔核(じかく)です。
[3]血液中の老廃物を分解除去する
薬やアルコールは肝臓で分解されます。これ以外にも血液の中の様々な不要となった物質、例えば赤血球などが分解してできたビリルビンは肝臓で処理され胆汁(たんじゅう)中に排泄され便として体外に出されます。しかし肝硬変になるとビリルビンが体に蓄積し、その結果全身が黄色くなります。これを黄疸(おうだん)といいます。とくに眼球結膜(白目)の部分が黄色くなります。また黄疸があると皮膚のかゆみがでてきます。食事として食べたタンパク質が分解する過程で、あるいは消化管内の常在細菌によりつくられ、アンモニアという中毒性の高い物質がでてきます。これも主として肝臓で解毒され尿素になり排泄されます。しかし肝硬変になるとアンモニアおよびその他の中毒物質が血液中に蓄積する結果、脳の代謝が障害を受けて様々な程度の意識障害や、手が震える「はばたき振戦(しんせん)」が出現します。これが肝性脳症です。
Hepatic Cirrhosis
【出典】 |
寺下医学事務所(著:寺下 謙三) 「 標準治療 」 |
| A D |
| 標準治療について | ||
|
| 関連電子書籍 | ||||||
| ||||||
| この言葉が収録されている辞典 |
標準治療

- 【辞書・辞典名】標準治療[link]
- 【出版社】日本医療企画
- 【編集委員】寺下 謙三
- 【書籍版の価格】5,142
- 【収録語数】1,787
- 【発売日】2006年7月
- 【ISBN】978-4890417162